職場に必ず一人はいる「自分はできる」と思い込み、やたらとアピールしてくる社員。
成果は伴っていないのに自己評価が高く、注意すれば逆ギレ、放っておけば周囲に不満を広げてチームの士気を下げてしまう…。
管理職としてどう向き合えば良いのか、頭を抱えた経験がある方も多いのではないでしょうか。
この記事では、私自身が実際に体験した「自分を過大評価する問題社員」との関わりをもとに、
- 問題社員の特徴
- 職場に与える悪影響
- 管理職が取るべき具体的な対応策
をわかりやすく解説します。
同じような悩みを抱える管理職やリーダーの方にとって、少しでもヒントになる内容になれば幸いです。
結論:否定でも放置でもなく「事実で返す」
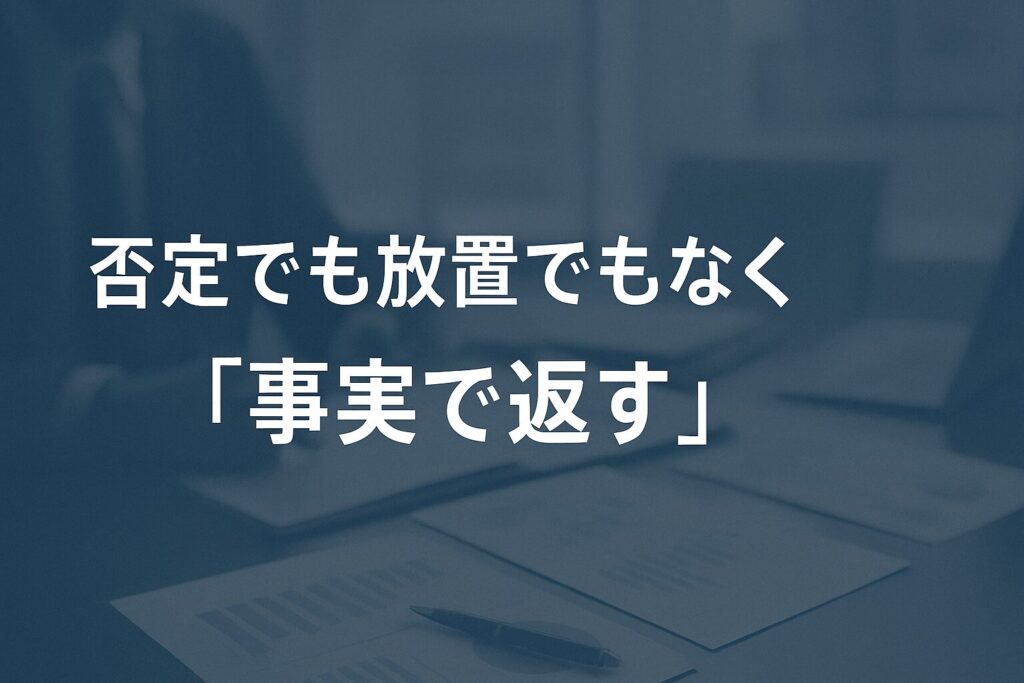
👉 最初に答えをお伝えします。
問題社員は否定しても放置しても逆効果です。必要なのは「事実ベースの評価」と「役割の明確化」で、冷静に向き合うことです。
職場には「自分はできる」と過剰にアピールし、実力以上に自分を評価している社員が存在します。
こうした社員はチームに摩擦を生み、周囲を疲弊させる厄介な存在です。
管理職が取るべき対応は、 頭ごなしに否定することでも、見て見ぬふりで放置することでもありません。
大切なのは「事実ベースの評価」と「役割の明確化」によって、本人の行動を軌道修正し、周囲への悪影響を最小化することです。
なぜ「自分はできる」と思い込む問題社員が厄介なのか
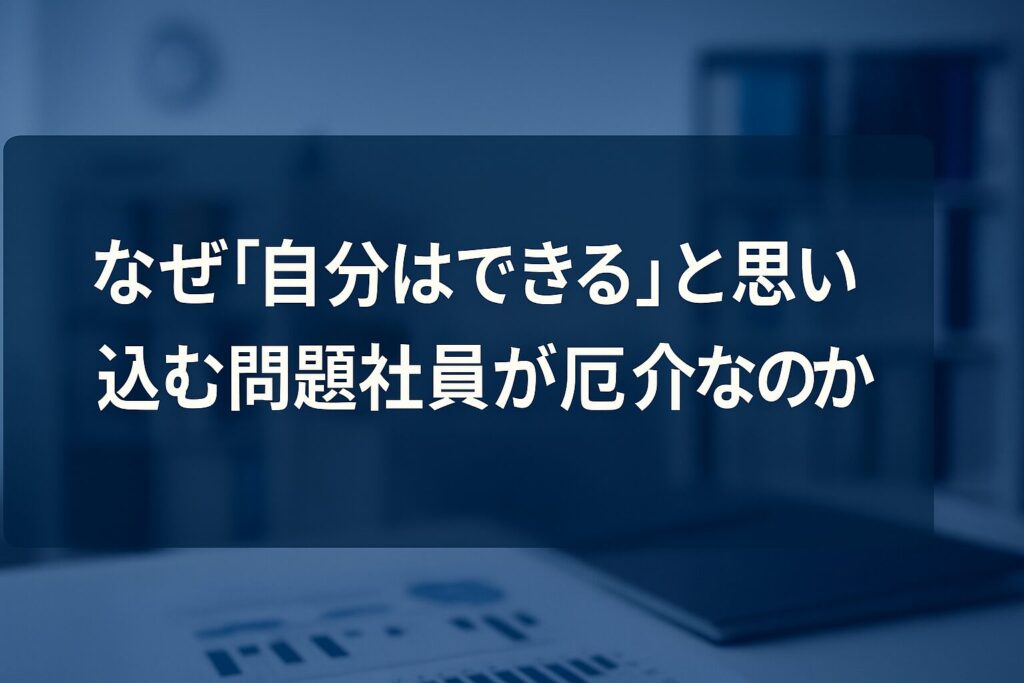
👉 自己評価が高すぎる社員は、指摘すると逆ギレし、放置すると職場を乱します。
ここでは「なぜ厄介なのか」を整理します。
| 管理職の対応 | 問題社員の反応 | 職場への影響 |
|---|---|---|
| 否定する | 逆ギレ・横暴な態度になる | 雰囲気が一気に悪化 |
| 放置する | 同僚に不満を語り続ける | 士気が下がり空気が淀む |
否定すると逆ギレして態度が悪化する
「できる」と思い込んでいる社員は、指摘されると逆ギレしやすく、横暴な態度に変わります。
結果、職場の雰囲気が一気に悪くなります。
放置すると不満を広げて職場が荒れる
放置すれば、同僚を捕まえて不満を延々と語り続けます。
チーム全体の士気が下がり、空気が淀んでしまいます。
実体験から見た「自分はできる」と思い込む社員の特徴
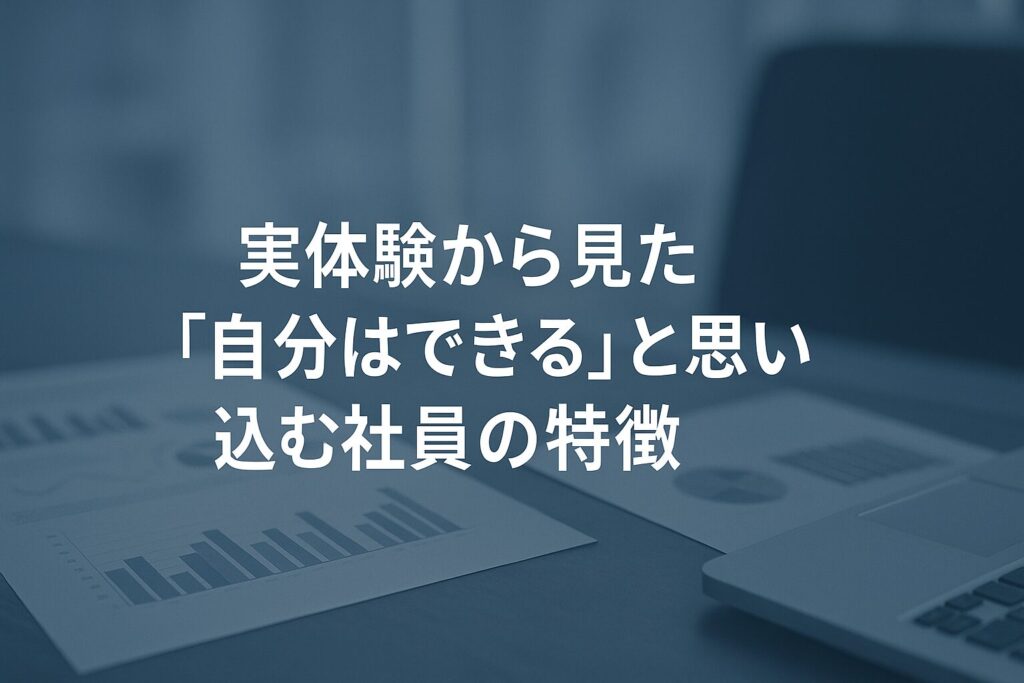
👉 私が実際に経験した「自分はできる」と思い込む社員の具体的な特徴を紹介します。
きっと「あ、うちにもいる」と思う方も多いでしょう。
| 特徴 | 具体例 | 周囲の反応 |
|---|---|---|
| 過剰なアピール | 古い技術を誇らしげに話す | 「また始まった…」と困惑 |
| 自己評価が高すぎる | 成果を誇張し「自分はできる」と思い込む | 誰も共感できない |
| 行動面の矛盾 | 暇でも手伝わず、浅い知識を披露 | 周囲が引くが本人は無自覚 |
| 評価への過剰反応 | 3時間不満を語る・横暴な態度 | 職場の空気が悪化 |
| 統計への誤解 | 「組合統計だから自分も上がるはず」 | 評価の本質を理解していない |
過剰なアピールで周囲を困惑させる
日常会話や朝ミーティングでやたらと発言。
「自分は知っているんだぞ」と誇示しますが、内容は古い技術やすでに消えたトレンドばかり。
成果を誇張し自己評価が高すぎる
20代の若手社員と比べ「自分の方ができる」と思い込み、成果が曖昧なことも「効率化した」「品質を上げた」と過大評価します。
暇でも手伝わず浅い知識を披露する
時間が余っても周囲を手伝わず、スキルアップの努力もしない。
代わりに浅い知識を周囲に披露して歩き回り、みんな引いているのに本人は無自覚です。
評価が悪いと態度が豹変する
昇給やボーナスの結果に納得できず、3時間も不満を語り続ける。
「そんな評価なら仕事をしない」とまで言い出します。
統計データを根拠に誤った主張をする
「労働組合の統計で◯%が良い評価だから、自分も上がるはず」と主張。
→ 個人評価と統計の違いを理解していない典型例でした。
正直に言うと、「退職してくれたら助かる」と思うほどでした。
問題社員が職場に与える悪影響
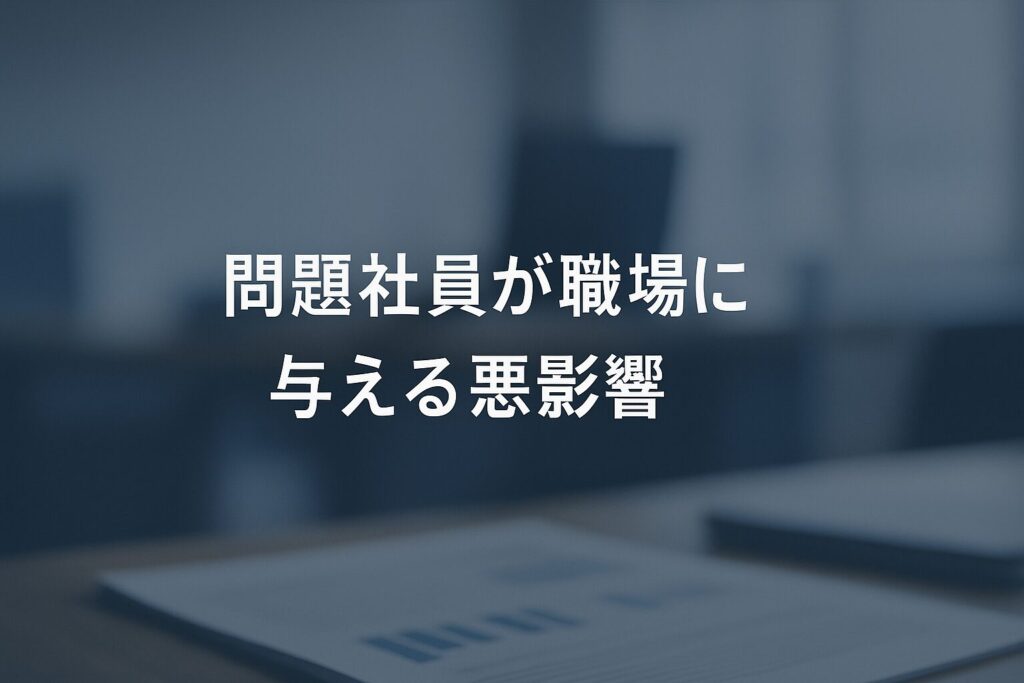
👉 こうした社員を放置すると、チーム全体に悪影響が広がります。
ここでは「職場に起きる具体的な弊害」を見ていきましょう。
チーム全体の士気が下がる
周囲がモチベーションを失い、「自分だけ頑張るのが馬鹿らしい」となります。
成長が止まり改善の意欲がなくなる
誤った自己評価のままでは学びも改善も止まり、成長が止まります。
周囲との温度差が信頼を壊す
「この人とは話が合わない」と感じさせ、チーム内の信頼感がなくなります。
管理職が取るべき具体的な対応策
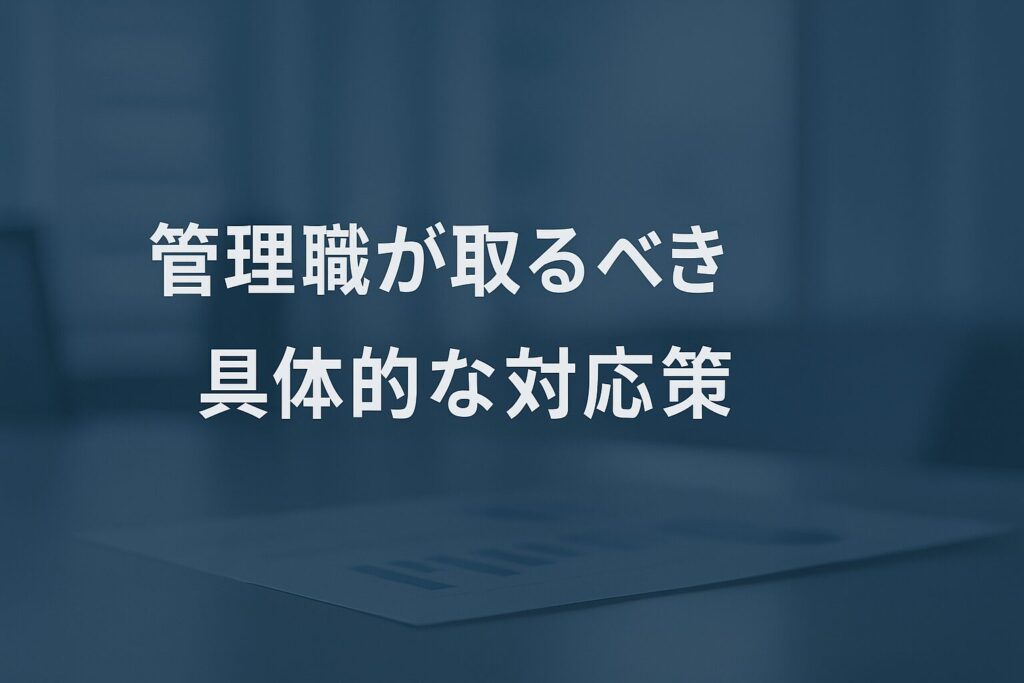
👉 ただ愚痴を言っても状況は変わりません。
管理職が実際にできる「具体的な対応策」を紹介します。
| 対応策 | ポイント |
|---|---|
| 事実ベースで評価 | 数字や実績で示し、感情論を避ける |
| アピールを成果に変える | 改善発表や資料作成を任せる |
| 役割を明確にする | 成果物を設定し、逃げ道をなくす |
| 不満の拡散を防ぐ | 1対1で時間を区切って対応 |
事実ベースの評価で冷静に伝える
「改善件数」「生産性」「不良率」など、数字や具体例を根拠にフィードバックします。
主観的な議論を避けられるため、納得感が高まります。
アピールを成果に変える仕組みをつくる
会議での改善発表や資料作成を担当させ、自己主張を「実績発表」に置き換えます。
明確な役割を与えて逃げ道をなくす
曖昧な仕事ではなく、成果物が見えるタスクを与え、評価=事実に直結させます。
不満を広げさせないための対応法
愚痴は1対1で時間を区切って対応し、同僚に文句を広げないようフォローします。
私が学んだ失敗と成功の対応法
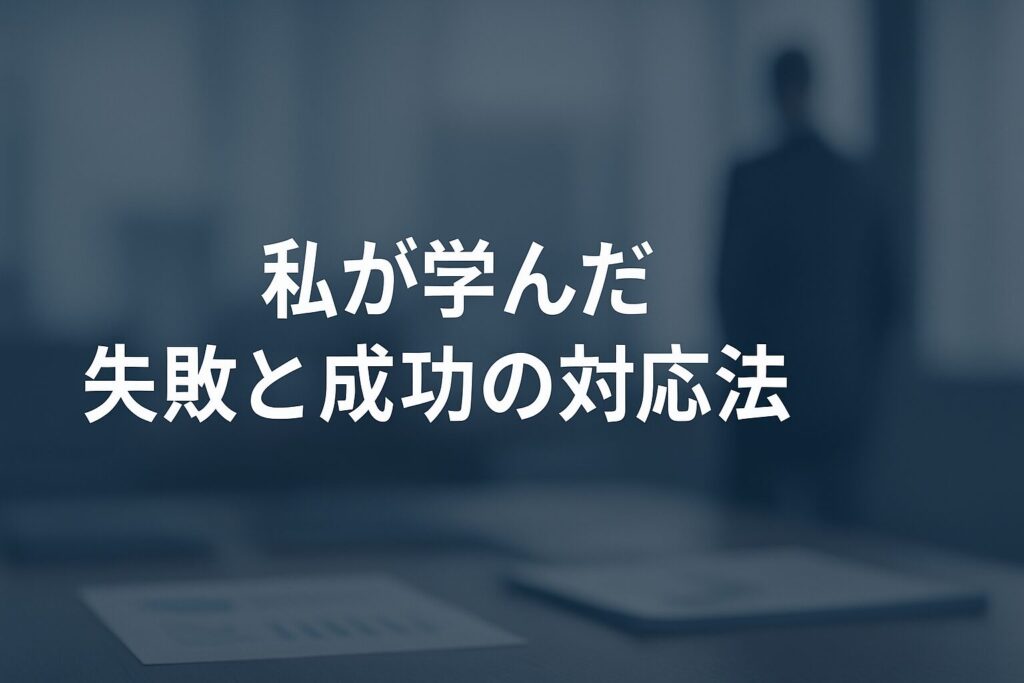
👉 私自身も最初は対応を間違えました。
失敗から学んだこと、成功につながったことをお伝えします。
| 失敗した対応 | 結果 | 改善後(成功例) |
|---|---|---|
| 強く否定した | 逆ギレ、雰囲気悪化 | データで冷静に示した |
| 放置した | 不満を拡散、士気低下 | 改善発表に誘導しプラス転換 |
否定・放置で失敗した例
- 強く否定 → 逆ギレで雰囲気悪化
- 放置 → 不満をばらまきチーム全体の士気低下
データで示し改善発表に活かした成功例
- データを根拠に評価を伝える
- 「できている点」と「改善点」を区分け
- アピール力を改善提案に活かすことでプラスに転換
管理職も人間だから、苦手な人は存在する
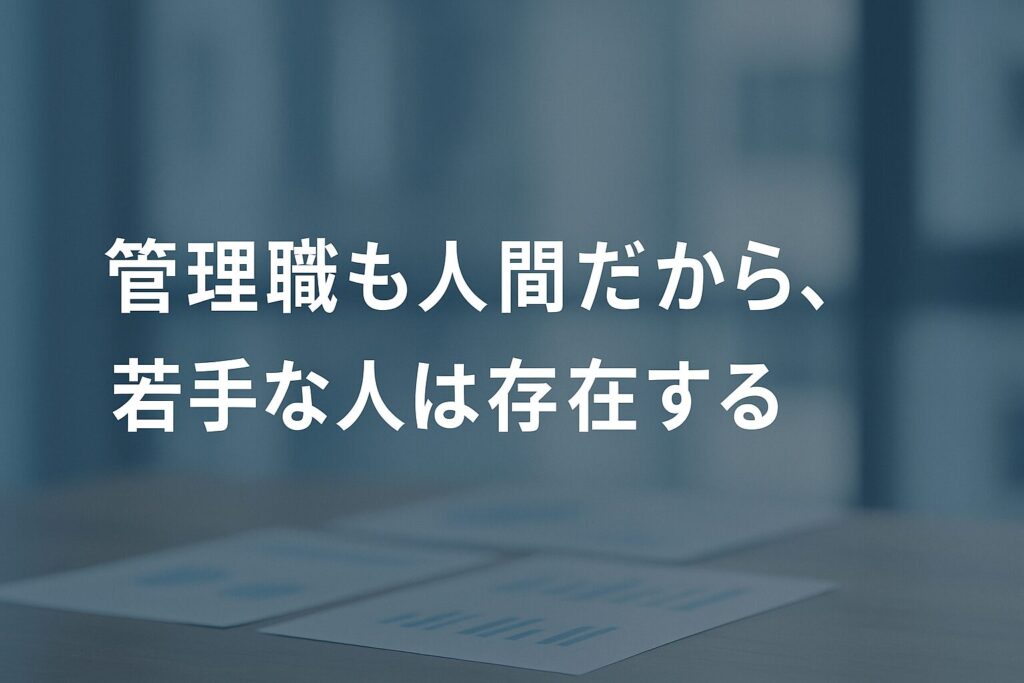
👉 管理職といえども人間です。どうしても合わない人はいます。
ここでは「無理をせず適切な距離を取ること」について正直に書きます。
私自身、このようなタイプの社員にはできるだけ近づかないようにしています。
管理職であっても人間です。どうしても相性が悪い人、正直「ダメだな」と思う人は存在します。
- 無理に仲良くする必要はない
- 最低限のライン(指示・評価・フォロー)は守る
- 適度な距離を取り、衝突を避ける
「適切な距離を取ることも一つのマネジメント」 です。
この正直さを持つことで、自分自身も少し楽になり、冷静に判断できるようになります。

まとめ:問題社員を武器に変える管理職の姿勢

👉 最後にまとめです。
問題社員を敵にするのではなく、チームの成果につなげる視点を持つことが大切です。
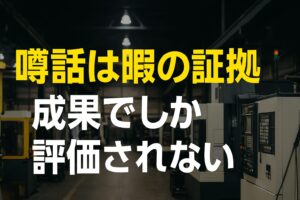
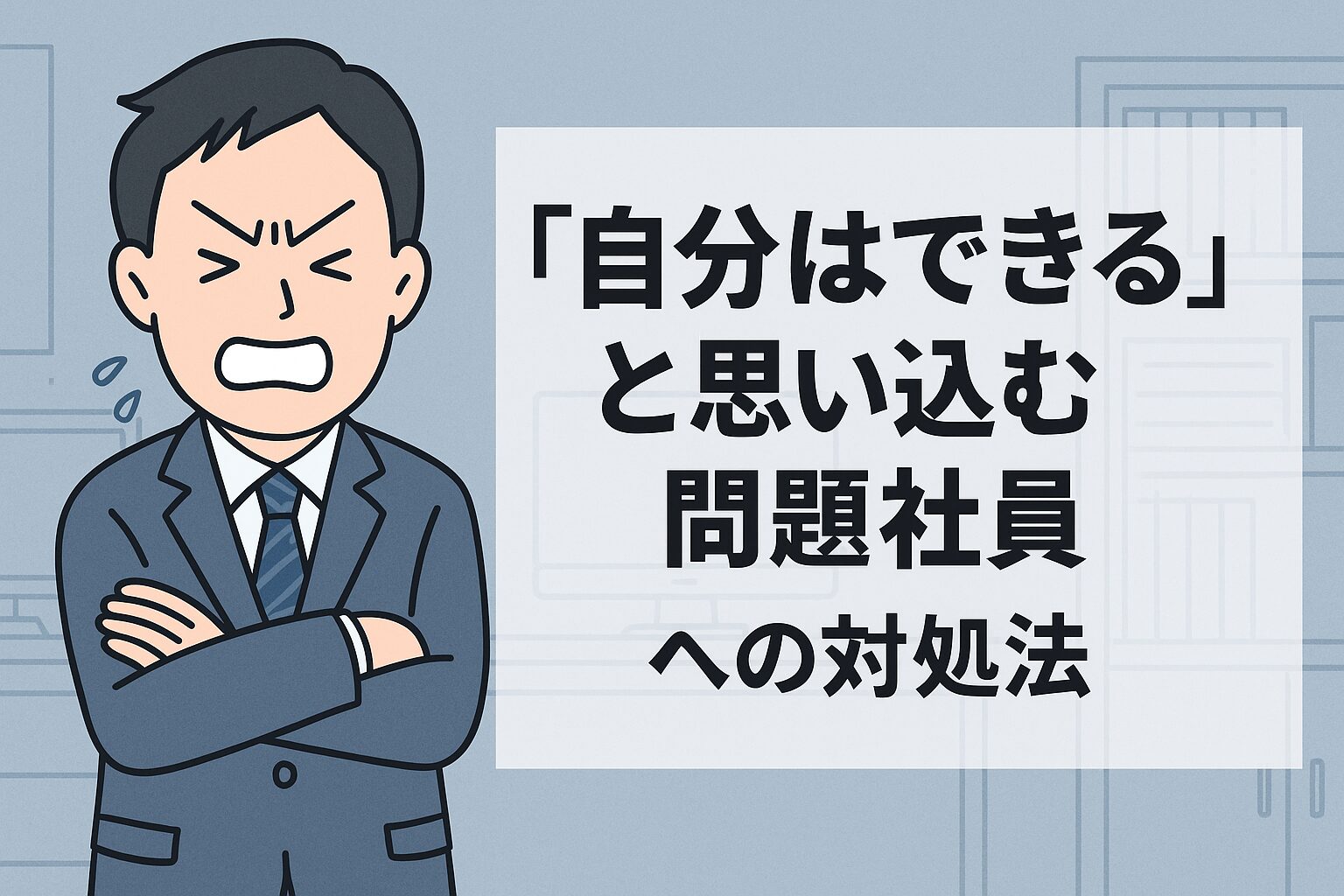





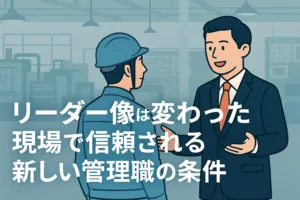


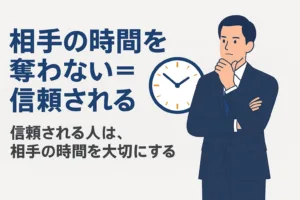
コメント